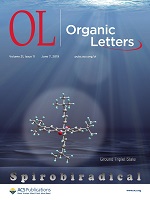テーマ1:ラジカル配位子と金属錯体の磁性
血中にあるヘモグロビンや葉緑素のクロロフィル、顔料プルシアンブルー、抗がん剤 (シスプラチン) や鉛中毒の解毒剤 (エデト酸カルシウムなど"金属錯体"は身近な物質群です。この金属錯体は、"金属イオン"と"配位子"から構成されており、様々な物性を示します。そのなかの1つとして、磁性材料への応用が盛んに行われています。
一般に、金属錯体を磁性材料へ応用する研究では、金属イオンが主役であり、配位子は磁性を示さないもの (非磁性, S = 0) が採用されています。本研究では、磁性を示す配位子 (常磁性, S ≠ 0) に着目して研究を行っています。このような常磁性配位子の利点は、新たに金属と配位子の間に磁気的な相互作用を導入することができます。この相互作用が橋渡し役となり、金属イオン同士の強い磁気的相互作用へと繋がり、磁気相転移温度の向上など磁性材料の向上に役立てることができます。
関連論文
Chem. Commun. 2014, 50, 2529.(Link);
Inorg. Chem. 2014, 53, 10794.(Link);
Inorg. Chem. Front. 2015, 2, 860.(Link);
Inorg. Chem. 2016, 55, 8140.(Link);
Inorg. Chem. 2017, 56, 3310.(Link);
Polyhedron 2017, 136, 30.(Link);
Eur. J. Inorg. Chem. 2021, 2021, 1130.(Link)
テーマ2:有機物の磁石
自動車、住宅、電化製品、航空、宇宙産業や医療機器など現代に至るまで様々な分野の発展に金属資源は利用されています。今後のIoTの発達は、更なる金属資源の需要増大が予想されます。金属資源の中でも、レアメタル (ニッケル、クロム、コバルトなど) や貴金属 (金や銀、白金族)、レアアース (ランタノイド元素にイットリウム、ストロンチウムを加えた類) と呼ばれる金属は市場価格が高く、資源に乏しい我が国ではこれら資源の利用は重要な課題です。
こうした情勢の中で求められる対応は、金属資源の消費抑制・再利用・代替技術の開発の3点です。当研究では、3点目の"代替技術の開発"を目指しています。具体的には、金属の代わりに有機化合物を用います。有機物は原油や植物などを原料としており、金属資源に比べて、"持続可能な社会"へ貢献します。近年、電池 (有機ラジカル電池) や表示材料 (有機EL) は、有機物による代替技術の開発が大きく進んでいます。これら電子材料に続くべく、当研究では、"金属を使用しない磁石 (有機磁石)"の研究・開発を行っています。
有機物を磁石とするためには、不対電子 (スピン) を持つ状態 (ラジカル) を利用します。この状態は一般に不安定ですが、化学的な処置 (立体保護や共鳴安定化) を施すことで、室温での単離や固体としての取り扱いが可能になります。1つの分子内に複数のスピンを有したオリゴラジカル化合物は、全てのスピンを同じ方向に揃える (高スピン状態) ことで金属と同等もしくはそれ以上の磁化を示すことができます。そのため、高スピン状態のオリゴラジカル化合物は金属に代わる磁性材料のビルディングブロックとして期待されています。
関連論文
Chem. Lett. 2017, 46, 188.(Link); AIP Conf. Proc. 2019, 2067, 020011.(Link); Org. Lett. 2019, 21, 3909.(Link); Tetrahedron Lett. 2020, 61, 152428.(Link)